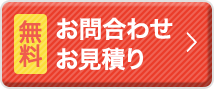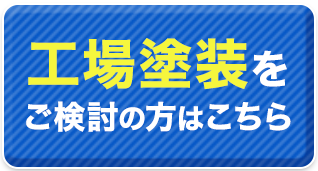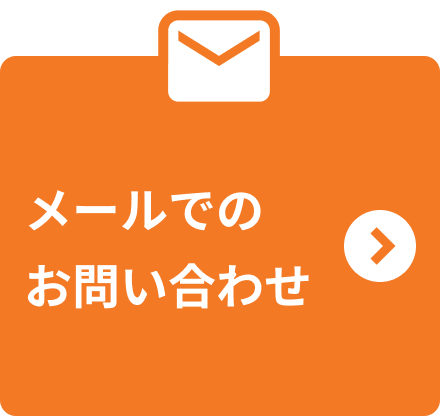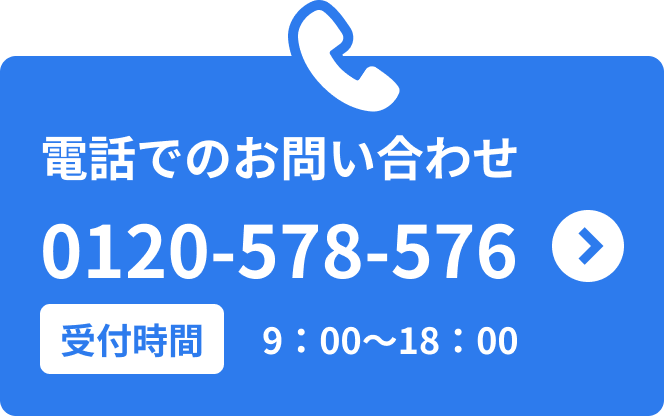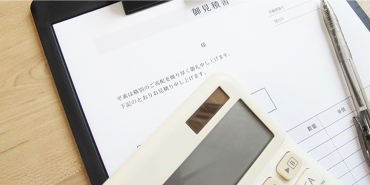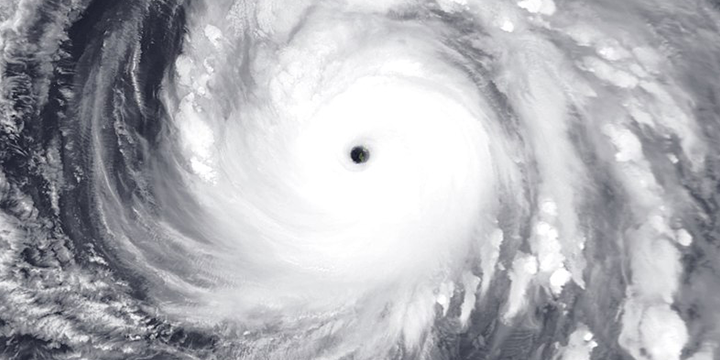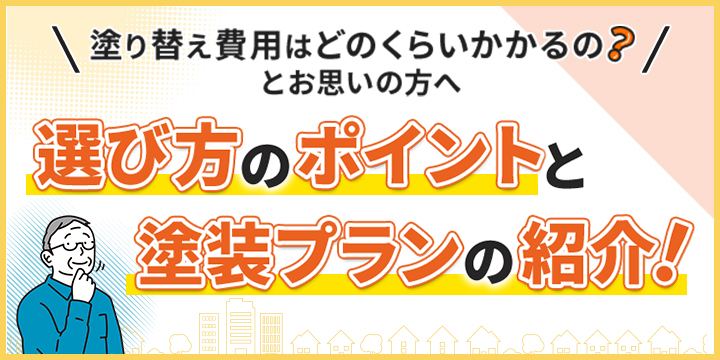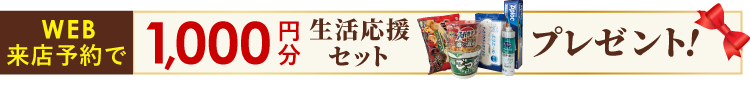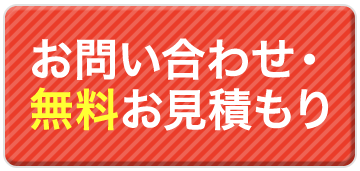- ホーム
- 記事カテゴリー
一棟オーナー必見!マンション外壁塗装の最適タイミングとコスト管理術
2025年10月21日(火)
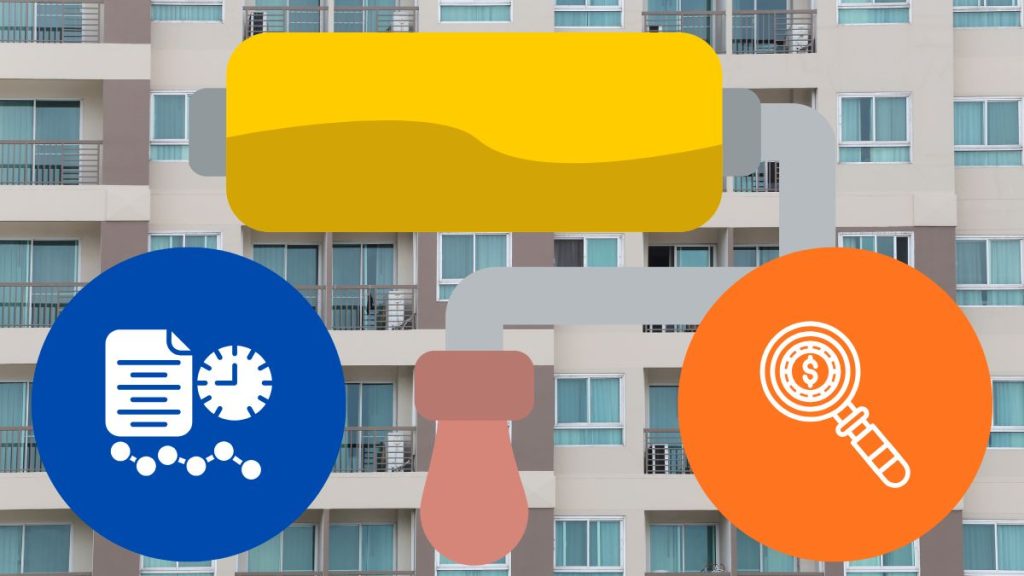
スタッフブログをご覧いただきありがとうございます!
愛知県豊田市の塗装会社、
代表取締役の丸山です!
マンションを一棟所有するオーナーにとって外壁塗装は、ただの美観維持ではなく資産としての価値維持や賃貸経営リスクの軽減に直結する判断です。
管理組合を通さないワンオーナー物件では、塗装周期・費用負担・施工時期の選定がすべてオーナーの責任になりやすく、キャッシュフローや入居者対応を含めた“経営計画”として捉える必要があります。
今回のお役立ちコラムでは、一棟オーナー視点でぜひ押さえておきたい外壁劣化のサイン・適切な塗装タイミング・コスト管理の視点を体系的に解説します。
▼合わせて読みたい▼
豊田市の屋根塗装はマルヤマにお任せ|アパートやマンションの屋根塗装におすすめの季節について
一棟オーナーが押さえるべき外壁塗装の周期と劣化サイン

外壁塗装をただ「10年に1回」と定型化するのは危険です。建物構造・素材・気候条件によって劣化スピードは大きく変動します。特に一棟オーナーでは、建物全体を俯瞰して周期判断をしなければ、修繕負荷が集中しキャッシュが逼迫するリスクがあります。
ここでは、定期的にチェックすべき劣化サインと、“オーナー判断型”のメンテナンス設計の考え方を示します。
10年ごとの「大規模修繕」とは異なる“オーナー判断型”メンテナンスの考え方
従来の分譲マンションでは「10〜12年ごとに大規模修繕を行う」という考え方が一般的ですが、一棟オーナー物件では必ずしもそれが最適とは限りません。大規模修繕を固定周期で実施すると、劣化が進行しすぎた状態で多額の費用を要したり、キャッシュフローに大きな負担がかかる場合もあります。
そこで有効なのが、“オーナー判断型”のメンテナンス戦略です。これは劣化の進行を段階的に見極め、小規模な補修を挟みながら、費用のピークを平準化していく方法です。たとえば、外壁に細かなひびやシーリングの硬化が見られる段階で部分補修を実施すれば、将来的な全面改修時の下地補修費を抑えることができます。
また、建物の構造や外壁材によっても最適な周期は異なります。鉄筋コンクリート造なら8〜12年ごとの塗り替えを基準に、途中で中間点検や軽補修を行うことで、資産全体の保全効率を高められます。こうした計画的メンテナンスを行うことで、突発的な大出費を避けつつ、長期にわたって安定した経営を維持できます。
資産価値を守るために見逃せない外壁の劣化サインと点検の目安
外壁の劣化は、見た目の変化が現れる前から静かに進行しています。早期に兆候をつかみ、軽微なうちに補修することが、結果的に費用を最小限に抑える最も効果的な方法です。
オーナー自身が把握しておきたい代表的な劣化サインは次のとおりです。
- チョーキング(手で触れると白い粉が付く)
- 微細なひび割れ(毛細クラック)
- シーリングの硬化・ひび割れ・隙間
- 塗膜の剥がれや浮き・膨れ
- コケや藻、黒ずみ、色あせ
これらの症状が出始めた段階で、部分的な補修や塗り替えを行うことで、劣化の進行を止めることができます。逆に放置すると、内部の鉄筋や下地まで水が入り込み、補修費が数倍に膨らむこともあります。
点検は「5年ごとの本格点検+2〜3年ごとの簡易点検」を基本にしましょう。高所の状態を確認するためにドローン点検を取り入れるのも効果的です。こうした定期観察を続けることで、外壁の寿命を延ばし、結果として資産価値を長期にわたって維持することが可能になります。
マンション一棟塗装のコスト管理術|収益性を落とさずに賢く修繕する方法

外壁塗装は高額投資になることが多いため、コスト管理と収益維持を両立する設計が不可欠です。単なる費用削減ではなく、キャッシュフロー視点からの整合性ある計画が成功のカギになります。ここからは、費用内訳と入居率維持の工夫に焦点を当てます。
塗料・足場・外構など費用の内訳とキャッシュフローへの影響
塗装工事では、塗料代だけでなく足場・下地補修・共用部・外構付帯部など複数の要素が費用を構成します。たとえば、一般的に外壁塗装で使われる平米単価の目安は2,000〜4,500円/㎡の範囲で、素材やグレードによって上下します。
またマンション大規模修繕全体では、平米単価で6,000〜15,000円前後のレンジも事例として報告されています。
施策としては、施工を分割して実施するタイミング設計(外壁→共用部→外構等)や、入居者の退去期を見据えた施工スケジュール調整を取り入れると、キャッシュフローを圧迫せずに運用できます。
賃貸経営を止めない!入居率を維持しながら計画的に施工するポイント
塗装工事は居住者にとってストレスとなることが多く、工期中の影響によって退去リスクが高まる可能性があります。これを抑えるポイントは以下です。
- 工期を複数期に分けて段階的施工
- 施工通知の事前案内・住民理解促進
- 夜間・休日の施工抑制
- 足場配置や養生設計で通行・採光・見通しへの配慮
また、施工中も見た目印象を損ねないカラー選定やアクセント配色を施すことで、むしろリニューアル効果を訴求できる場合もあります。こういった配慮を含めた施工計画が、経営を止めずに資産価値向上を両立させる鍵になります。
▼合わせて読みたい▼
アパート外壁塗装の費用相場と予算計画|豊田市の賃貸オーナーが押さえるべきコスト戦略
FAQ|一棟オーナーが知っておきたいマンション外壁塗装の疑問

一棟オーナーとして外壁塗装に取り組む際、疑問を抱くことは当然です。特に「築年数・居住者対応・会計処理・補修範囲」などは、経営視点で判断すべきテーマです。
以下のFAQでは、これらオーナーならではの疑問に結論ベースで答えつつ、実務的な注意点を交えて解説します。
Q1.築年数が浅くても塗り替えを検討すべきケースはありますか?
結論から言えば、築年数が浅くても劣化要因が強ければ塗り替えを検討すべきです。築10年未満でも、立地の過酷度(海岸近辺、幹線道路沿い、排ガスの影響など)や新築時の下地処理・施工品質の差、使われた塗料グレードの違いにより塗膜劣化・チョーキング・ひび割れなどが早期に現れることがあります。
実際、海岸線近くでは7〜8年で塗膜劣化が顕著になる例も報告されています。また、国交省のガイドラインや調査では12〜15年周期が大規模修繕の目安とされていますが、これはあくまで「通常想定の条件下での標準」であり、実際には現場診断で劣化状況を見て判断すべきです。
補足として、築浅物件であっても以下のようなケースは特に注意が必要です。
- 新築時の施工で下地処理が不十分だった場合
- 外壁素材(モルタル・リシン吹付など)が劣化しやすいタイプの場合
- 建物が強風・直射日光を受けやすい立地(屋上露出、南面壁面など)
- 周囲の環境(海風・工場排ガス・砂埃)による劣化促進
これらの条件が重なっていれば、築10年未満でも早期点検・補修を前倒しで計画しておくほうが、後々の大規模補修リスクを下げられます。
Q2.居住者がいる状態でも塗装工事は可能ですか?
可能です。ただし施工計画と配慮が不可欠です。完全な居住停止をせずに進めるケースも多く、むしろその方が賃料収入を確保しながら修繕を進められます。ただし、居住者への迷惑リスクを最小化する工夫が必須です。
主な配慮点としては以下があります。
- 施工スケジュールを複数期に分ける(部分施工や区分施工)
- 通行動線・採光・玄関まわりの養生や開閉確保設計
- 作業時間帯制限(夜間・休日の騒音抑制)
- 事前案内・説明文書配布・仮設足場や養生の安全対策
- 換気・臭気対応(塗料の揮発性物質への配慮)
こうした配慮を徹底すれば、入居者クレームや事故リスクを抑えながら、塗装工事を実施できます。施工業者選定時には「居住者対応実績」「事故防止策」を確認するようにしましょう。
Q3.法人経営の物件では経費計上や減価償却はどう扱えばいいですか?
外壁塗装の費用が「修繕費」扱いか「資本的支出」扱いかで経費計上方法が変わるため、用途・金額・改修内容を基準に分類して処理する必要があります。
主な判断基準と処理方法は次の通りです。
- 修繕費として処理:建物の現状維持・回復を目的とする部分的工事で、外観変更を伴わない補修的施工。
→当年度に一括経費計上可能。 - 資本的支出(減価償却対象):建物の価値を向上させる意図で大規模変更を伴う施工、または耐久性を長期化させるような仕様アップ等を含む場合。
→建物本体と同じ耐用年数で減価償却することが認められるケースがあります。
実務上の目安として、工事金額が20万円未満であれば修繕費扱いされやすいとする運用もあります。
また、中小法人には「少額減価償却資産の特例」があり、取得価額が30万円未満の資産なら全額を損金算入できる可能性がある制度もあります。
ただし、これらの判断は税務リスクに直結するため、事前に税理士等専門家と相談・確認することが強く推奨されます。
Q4.塗装だけでなく防水や鉄部補修も同時に行うべきですか?
可能であれば一括で同時施工することを強くおすすめします。分けて行うと将来的に重複作業・足場コスト増・工期延長のリスクがあるためです。特に以下の理由から同時施工のメリットが大きい:
- 足場を再設置するコストを削減できる
- 下地補修の重複や仮設養生の重複を避けられる
- 防水層や鉄部の劣化進行を抑えて建物全体の劣化抑制につながる
- 入居者への施工ダメージを一度に抑制できる(スケジュールの短縮)
ただしすべてを一度に行うには資金負担が重くなるため、以下の判断軸をもとに優先度を付けて設計するとよいでしょう:
- 劣化度合い(雨漏りリスクが高い箇所は優先)
- 建物構造上の劣化連鎖(外壁からの雨水浸入で鉄骨/コンクリート内部に影響が出る可能性)
- キャッシュフロー制約を踏まえ、段階的な施工分割の検討
結果的に、塗装・防水・鉄部補修を統合したメンテナンス設計が、長期的な保全効率を高め、将来の追加コストを抑える最善の戦略になります。
マルヤマが導く!一棟マンション外壁塗装を成功させる最終判断ガイド

一棟マンションの外壁塗装を検討する際、最も重要なのは「どのタイミングで・どれだけの仕様で・どの順序で施工するか」の意思決定です。
今回のお役立ちコラムでお伝えしたように、劣化サインの早期把握と、キャッシュフローを意識したコスト設計、入居者対応を緻密に考えた施工体制が成功の鍵になります。
まずは、塗装周期を固定概念にせず、現状に即した判断をすることから始めましょう。次に、塗料・足場・補修項目の内訳を前提に、無理のない予算配分と段階的施工を設計します。
最後に、施工中も入居率に悪影響を与えない工期配慮やデザイン演出を取り入れることで、経営を止めずに資産価値向上を実現できます。
判断に迷うときは、プロタイムズ豊田永覚店/株式会社マルヤマによる無料劣化診断・仕様提案をぜひご利用ください。問い合わせフォーム・メール・電話でのご相談はもちろん、ショールーム来店も歓迎いたします。
一棟オーナーだからこそできる、賢い外壁塗装戦略を共に描きましょう。
人気記事

古い家の外壁は何が多い?外壁の種類と特徴を徹底解説
スタッフブログをご覧いただきありがとうございます! 愛...

危険木補助金とは?伐採費用が安くなる制度の活用法
スタッフブログをご覧いただきありがとうございます! 愛...

【ご報告】2年連続デザイン塗装でグランプリを獲得しました!
スタッフブログをご覧いただきありがとうございます! 愛...


 0120-578-576
0120-578-576