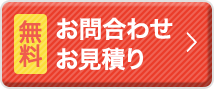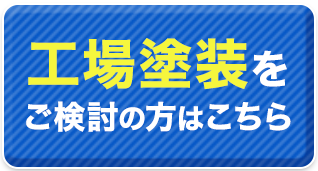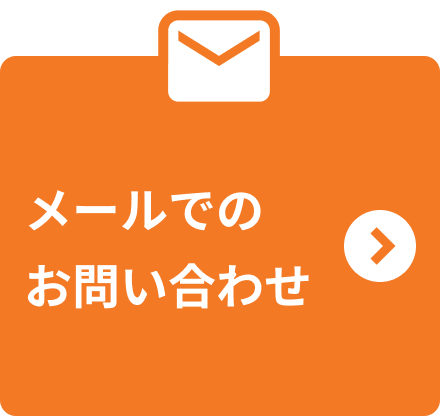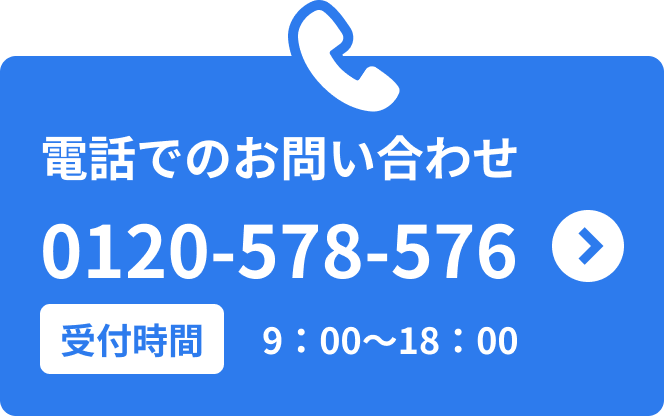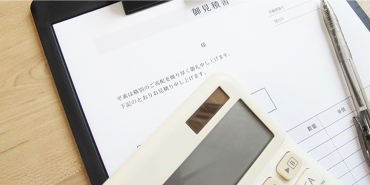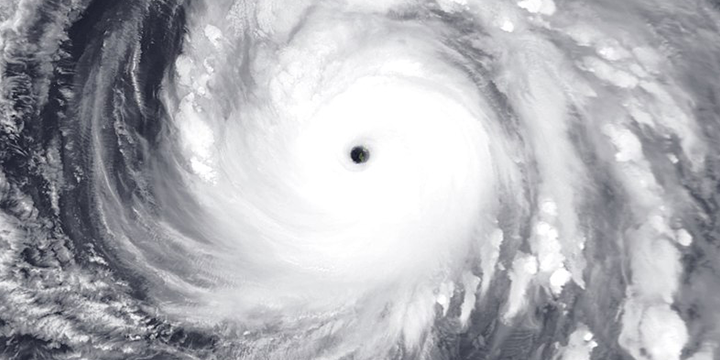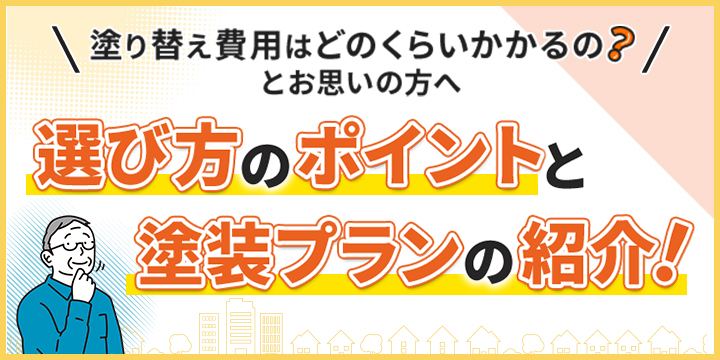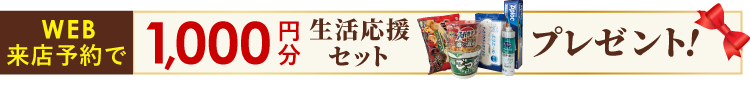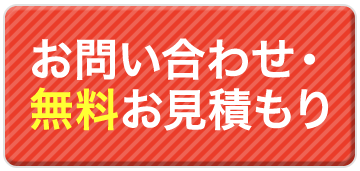- ホーム
- お役立ちコラム
お役立ちコラム
古い家の外壁は何が多い?外壁の種類と特徴を徹底解説
2025年07月19日(土)

スタッフブログをご覧いただきありがとうございます!
愛知県豊田市の塗装会社、
代表取締役の丸山です!
築30年以上の古い住まいや100年近い歴史のある古民家は、2025年現在の住まいとは材質から違うことがあります。築30年と言えば、1995年です。当時は最先端の住まいでも、30年も経過すれば劣化が進むのは当然と言えます。
不具合は見えないところで、進行している可能性もあるのです。一度に大量の雨水が侵入しなくても、長期間かけて雨漏りが続いていれば、腐食が発生しているかもしれません。外壁材も見えない死角でひび割れが発生している可能性もあります。
修繕工事だけではなく、古い住まいを相続してリフォームを考えている方もいるでしょう。既存の外壁を活かす場合、材質や特徴への理解も求められます。
そこで今回のお役立ちコラムでは、古い家の外壁には何が多いのか?種類や特徴について、くわしくお話しします。
古い家の外壁を放置すると何が起こる?まず知っておきたい劣化のリスク

築30年以上でメンテナンスもほとんどしていない住まいは、雨漏りのリスクが高いと言えます。雨水が建物内部に侵入すると、柱や梁のような構造躯体が濡れることになるのです。
木材の中の水分が多すぎると、木材腐朽菌という、木材を餌にする菌類が増殖します。木材が腐ると、建物全体の耐久性は低下するのです。
また、腐朽した木材に誘われて、シロアリが来るかもしれません。断熱材も濡れると機能性は低下します。快適性も耐久性も低下しますから、古い住まいの劣化は、まさしく住めなくなる建物になることを示すのです。
築30〜40年の住宅は、当時の素材の耐久性や施工方法も現在とは異なる場合もあります。たとえば耐震性の問題です。旧耐震基準は1981年6月1日以前、それからいくつか新耐震基準として変更されています。
1995年阪神・淡路大震災の被害の影響で2000年代にもあり、いくつか変遷があるのです。この点を考えると、古い住まいは、現状の耐震基準を満たしていない可能性があります。
参照:国土交通省 共同住宅ストック再生のための技術の概要(耐震性)
修理費用が膨らむ前に点検と見直し
住まいは劣化が進むほど、費用がかかります。劣化が進む前に点検や補修をすることで、数万円〜数十万円の金額で済む場合も多々あるのです。
問題は放置した場合でしょう。屋根でも外壁でも、最も金額がかかるのは屋根の葺き替えや外壁の張り替えです。両方とも100万円以上かかってもおかしくない大規模リフォームになります。
「現状、何も起きていないから大丈夫」と油断は禁物です。信頼できるリフォーム業者や外壁・屋根の塗装専門業者に点検ぐらいは相談しておいたほうがいいでしょう。早めに手を打てばその分、経済的な負担も軽くなります。
古い住まいに使われていた外壁材の種類と特徴

ここからは古い住まいに使用されていた、特徴的な外壁材について
木板張り(下見板・羽目板など)
昭和初期や古民家に見られる伝統的な外壁材です。木の板を貼り付けて外壁にしています。木の温かみや高い通気性がメリットです。反面、湿気や紫外線に弱いデメリットがあります。木板張りは10年に一度、塗装工事や張り替えが必要です。また、木材ですからシロアリや木材腐朽菌被害には、とくに注意しなければなりません。
モルタル壁(リシン・スタッコ・吹付け仕上げ)
昭和30〜50年代の戸建て住宅に採用されてきました。セメントと砂と水を練り上げて作っています。メリットは、高い耐火性や遮音性を有している点です。
継ぎ目がない仕上がりのため、壁全体が一体となりすっきりとしています。砂粒状の骨材を吹き付けるリシンや、スタッコなど、さまざまな仕上げ方法があり、個性を演出できるのもポイントです。
デメリットは、地震による揺れや膨張収縮による動きにより、ひび割れが発生しやすい点でしょう。モルタルは吸水性があるため、定期的な塗装工事は必須と言えます。
トタン
倉庫や簡易的な住まいによく採用された金属製の外壁です。軽量ですし、施工も短期間で済みます。初期費用も他の外壁材と比較すると安く抑えられるのがメリットです。
ただし、トタンには錆びつきやすいという大きなデメリットがあります。表面の塗膜が劣化したり傷ついたりすると、鋼板がむき出しになるため、錆びが発生しやすいのです。
海岸地域だと塩害による錆びには、日常的に注意しなければなりません。また、熱伝導率が高いため、断熱性は期待できません。真夏は暑く、冬は寒いため、遮熱塗料や断熱材の選定が快適性保持の鍵を握ります。
初期型の窯業系サイディング
平成初期の住まいに多く見られるのが窯業系サイディングです。セメントと繊維質を混ぜた板状の外壁材で、カラーバリエーションが豊富で高いデザイン性を備えています。
ただ、初期の窯業系サイディングは現在にはないデメリットもあるのです。現在の窯業系サイディングと比較すると、紫外線や雨に対する耐久性は低いと言えます。
外壁塗装で形成した塗膜が劣化すると、サイディングボードは水分を吸収しやすくなるのです。そのため反りが発生しやすいのは弱点と言えます。
シーリング材も現代と比較すると、耐久性の低さは弱点です。シーリング材が劣化すると外壁材の間に隙間ができます。雨漏りの原因になるため要注意です。
外壁材自体は耐用年数が長くてもメンテナンスは前提

昔の外壁材も耐用年数自体は極端に短いわけではありません。モルタルでも約30年〜50年以上は保つとされています。トタンでも約10年〜20年、初期型の窯業サイディングも約20年〜40年です。木板張りでも20年以上は保つと言われています。
ただ、すべての外壁材に言えることですが「外壁塗装」や「細かな補修」前提の耐用年数と考えてください。外壁塗装をしなければ、10年過ぎると劣化します。塩害が多い場所なら、トタンなら10年保たないかもしれません。
古い住まいの外壁材でもメンテナンスを定期的に行っているなら、良好な状態を保てている可能性はあります。
築年数別で考える「外壁の寿命と劣化症状」
築20年〜30年なら、塗膜の劣化も過ぎて限界を迎えている可能性があります。色あせもありますし、シーリングもはがれやひび割れも起きているでしょう。早めに再塗装や補修が必要です。
築30〜40年もすれば、ひび割れや塗膜はがれのほか、下地木部の腐食などが発生していてもおかしくありません。部分補修では対応しきれないケースが増えます。
築40年以上だと、外壁材は寿命を迎えている状況です。全面張替えや断熱改修を含む大規模リフォームが求められます。
リフォームで選ばれている最新の外壁材とその特徴

2025年現在、選ばれている外壁材としてはガルバリウム鋼板が挙げられます。トタンの進化版で、トタンの弱点を克服しているのが特長です。
錆に強いですし、軽量で建物への負担が少なく耐震性も高いと言えます。見た目もスタイリッシュで、古民家再生でも選ばれることが多い外壁材です。耐用年数も20〜30年を誇ります。
サイディング系
高耐候窯業サイディングは、耐用年数が15〜30年もあり、初期の窯業系サイディングより高性能です。デザイン性やカラーリングも豊富で、モダンで個性を出したい方に適しています。
樹脂系サイディングも選択肢の1つです。海外での需要は高いのですが、日本では取り扱いが少なく高価な部類となります。ただ、湿気や雨、凍害や塩害に強く変質がほとんどなく、退色がないのもメリットでしょう。
古い外壁のリフォームは「マルヤマ」に相談を!外壁材の特徴を知って後悔しない選択を

築30年以上の住まいには、モルタル・木板張り・トタン・初期型窯業系サイディングなど、時代ごとに異なる外壁材が使われています。
いずれも定期的なメンテナンスを前提に設計されているため、放置すれば雨漏り・腐食・構造材の劣化など、深刻なトラブルに発展するリスクがあります。外壁材の寿命を正しく理解し、築年数に応じた補修やリフォームを計画することが大切です。
株式会社マルヤマ/プロタイムズ豊田永覚店では、古い外壁材の状態を的確に診断し、張り替え・カバー工法・塗装など、住まいに最適な改修プランをご提案可能です。
将来的なコストを抑えながら快適な暮らしを実現するためにも、【問い合わせフォーム】【メール】【電話】【ショールーム来店】から、お気軽にマルヤマへご相談ください。
人気記事

古い家の外壁は何が多い?外壁の種類と特徴を徹底解説
スタッフブログをご覧いただきありがとうございます! 愛...

グリシェイドグラッサ屋根材塗装ガイド:耐久性向上の秘訣と業者の選び方
スタッフブログをご覧いただきありがとうございます! 愛...

外壁の汚れが気になる!排気ガスや鉄粉の汚れは落とせる?対策方法は?
スタッフブログをご覧いただきありがとうございます! 愛...


 0120-578-576
0120-578-576