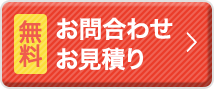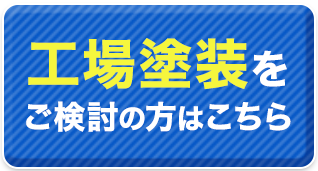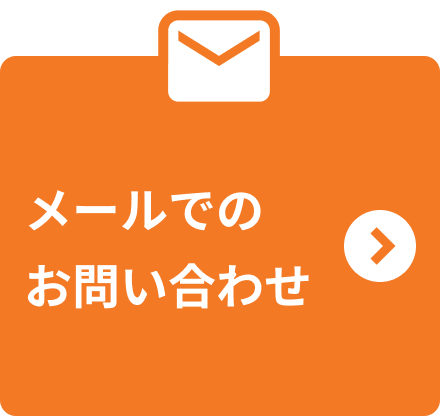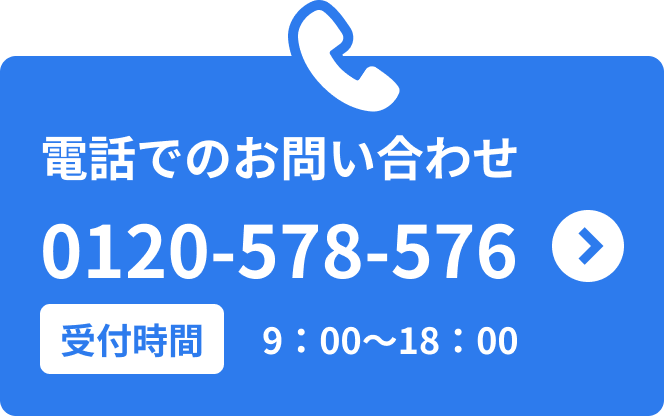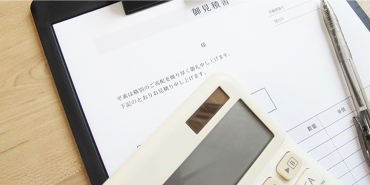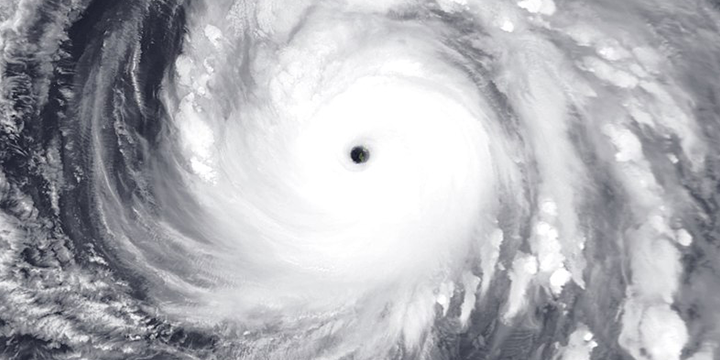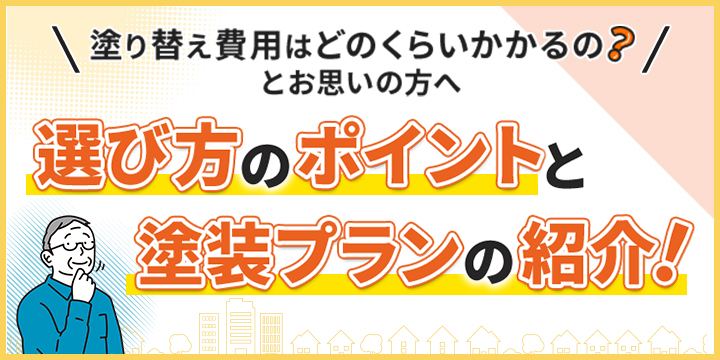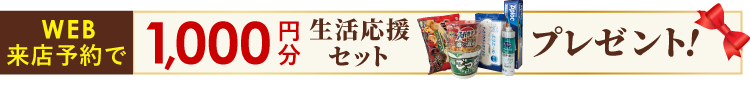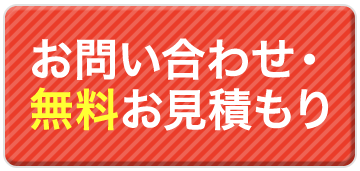- ホーム
- お役立ちコラム
お役立ちコラム
工場の雨漏りは「屋根だけが原因」じゃない!外壁・シーリング・配管の盲点をチェック
2025年05月08日(木)

スタッフブログをご覧いただきありがとうございます!
愛知県豊田市の塗装会社、
代表取締役の丸山です!
「屋根は数年前に補修したばかりなのに、また水が漏れてきた」
そんな経験をされた工場担当者は少なくありません。
実は、雨漏りの原因が屋根だけにあるとは限らないのです。外壁のひび割れや、シーリングの劣化、さらには設備配管の貫通部など、見落としがちな箇所からも雨水は侵入します。
特に築年数が経過した工場ほど、複合的な原因が絡み合って再発リスクを高めています。屋根を修理したのに直らないということは、他の場所にも何らかの「隙」があるサインです。
今回のお役立ちコラムでは「屋根以外に潜む工場の雨漏り原因とその見極め方」について解説します。
▼合わせて読みたい▼
工場の外壁塗装を後回しにしていませんか?老朽化による倒壊リスクと補修の重要性
屋根だけ直しても雨漏りが止まらない理由

工場の雨漏りは「屋根を直せば解決する」と思い込んでいませんか?もちろん屋根の劣化は主要な原因のひとつですが、実際には外壁のクラックやシーリングの剥離、配管まわりの隙間など、見落としがちな箇所からも水が侵入することが多々あります。
特に雨漏りの再発が続いているケースでは、屋根以外に複数の原因が潜んでいることが少なくありません。
調査範囲が屋根だけに限定されていると、本質的な改善には至りません。再発を繰り返せば、そのたびに点検・補修のコストが発生し、結果的に損失が膨らむ一方です。根本原因を見逃さないためには、建物全体を見渡す視点が欠かせません。
工場の雨漏りは「複数原因」が当たり前になっている
現代の工場は複雑な構造をしており、雨漏りの原因も一箇所にとどまらないのが一般的です。屋根・外壁・シーリング・配管など、それぞれに経年劣化のリスクがあり、どこか一箇所でも不具合があれば、そこから水が侵入する恐れがあります。
また、以前に屋根補修をした際、その時点で見落とされていた他の経路から水が入ってくるケースもあります。特に外壁の継ぎ目や出入り口の上部など、風雨の影響を受けやすい部位は注意が必要です。
こうした複合的な要因は、一見してわかりにくいため、「屋根さえ直せばOK」という認識では十分な対策とは言えません。
屋根と外壁のつなぎ目=シーリング劣化が盲点
工場の屋根と外壁が接する部分は、構造的にも水が溜まりやすく、シーリング(コーキング)で防水処理がされていることが一般的です。ところが、このシーリング材は紫外線や風雨にさらされることで徐々に硬化・剥離し、わずかな隙間から雨水が入り込むようになります。
見た目ではわかりにくいものの、劣化が進行すると目地が割れて、雨水が建物内部へと浸透していきます。これが繰り返されると、内壁や断熱材が濡れ、カビや腐食の原因にもなります。
屋根の修理をしても雨漏りが収まらない場合は、この接合部のシーリング劣化を疑うべきです。
配管や設備周辺の雨水侵入経路を見逃していないか
工場では空調や配線、給排水など多くの配管が外壁を貫通しています。こうした配管の取り合い部には、本来シール材やカバーで雨水の侵入を防ぐ構造が施されていますが、経年とともにその効果は薄れ、隙間が発生することがあります。
また、増設や移設時に適切な処理がされていないまま放置されている配管も多く、そこが「雨水の侵入口」になっているケースも少なくありません。
さらに、屋外設備の基礎部と壁の間にできた小さな隙間、排気フードの取付部、古い換気口などもリスク箇所です。これらは見た目には問題がなさそうでも、雨の吹き込みや水の跳ね返りで少しずつ内部が侵食されていきます。再発を防ぐためには、こうした細部の確認が不可欠です。
▼合わせて読みたい▼
工場の屋根が雨漏り!?操業停止のリスクを防ぐために今すぐ確認したい症状とは
工場の外壁・シーリングで起こりやすいトラブル

「雨漏り=屋根」と思われがちですが、実際には外壁やシーリング部分にも多くのリスクが潜んでいます。特に築10年以上が経過した工場では、目立たない場所でじわじわと劣化が進み、気づかぬうちに建物の内部まで水が浸入してしまうケースが後を絶ちません。
しかも、こうした劣化は初期症状が非常に小さいため、発見が遅れがちです。
工場の外壁やシーリングで実際に起こりやすいトラブルと、その発生メカニズムがわかれば、再発の芽を事前に摘み取ることができ、メンテナンスの質も向上します。
外壁のひび割れから内部に水が浸入する仕組み
工場の外壁に現れるヒビ割れは、単なる表面上の問題ではありません。雨水は非常に細い隙間からでも侵入する性質があるため、ヘアクラック(幅0.3mm以下の微細なヒビ)であっても油断は禁物です。外壁材の下には断熱材や構造材があり、そこに水が染み込むと建材の強度が低下してしまいます。
また、水分を含んだ断熱材は乾きにくく、内部で湿気がこもることでカビや結露を引き起こす温床になります。これにより、壁の内部から腐食が進行し、最終的には外壁が浮いたり剥がれたりといった物理的なトラブルへと発展します。
ヒビは外壁劣化の入口であり、初期の段階での発見と補修が極めて重要です。
シーリング材の寿命と再施工のタイミング
シーリング材(コーキング)は、外壁の継ぎ目や窓枠まわりなど、雨水が侵入しやすい部位に用いられる防水素材です。このシーリングは経年により硬化・ひび割れ・剥離を起こし、やがて本来の防水性能を失います。一般的なシーリング材の寿命は約10年前後とされており、建物と同じく定期的なメンテナンスが必要です。
ひび割れたシーリングから侵入した雨水は、下地材を腐食させ、外壁内部の鉄部や配線類にダメージを与えることがあります。特に注意が必要なのは、硬化して弾力を失った古いシーリングです。外壁の動きに追従できなくなり、微細な振動や温度変化によって簡単に剥がれてしまうからです。定期的なチェックと、10年を目安にした再施工が推奨されます。
設備増設や配管工事後に劣化が進む背景とは
工場では、空調機器や配管、ダクトなどの設備を後から追加・移設することがよくあります。こうした工事の際、外壁に穴を開ける、配管を通すといった処理が行われますが、その後の防水処理が不十分だった場合、そこが雨漏りの「新たな侵入口」となってしまうのです。
特に外注業者が複数関わるようなケースでは、防水の責任があいまいになり、十分な処理がされていないことも珍しくありません。時間の経過とともにパッキンが劣化したり、シーリングが剥がれたりして、知らぬ間に雨水が内部へと侵入していきます。
こうした「二次的な雨漏りリスク」を未然に防ぐには、設備工事のたびに防水処理を点検し、記録として残しておく体制づくりが求められます。
▼合わせて読みたい▼
豊田市の屋根塗装はマルヤマにお任せ|工場が雨漏りする原因と対策方法
再発を防ぐために必要な「総合的な雨漏り診断」

「屋根は修理した」「外壁も見た目に異常はない」それでも雨漏りが再発してしまう。そんなケースでは、ピンポイントの補修だけでなく、建物全体を対象にした総合的な雨漏り診断が欠かせません。
なぜなら、雨漏りは単独要因で起こるとは限らず、複数の隠れた経路が連携していることがあるからです。
実際、専門業者の診断によって、屋根の隙間と配管周辺の劣化が同時に雨水侵入に関与していた例は珍しくありません。表面的な症状だけに目を向けるのではなく、建物の構造全体とその周辺環境を含めた立体的な視点が必要になります。
再発を防ぐには、本当の原因を突き止めるプロの力を借りることが最短ルートです。
目視ではわからない侵入経路の特定方法
雨漏りは、目に見える症状と原因の場所が一致するとは限りません。たとえば天井のシミが出ている場合でも、実際に水が侵入しているのは数メートル離れた屋根のつなぎ目だったり、外壁のシーリングだったりします。このような「隠れた経路」は、目視点検だけではまず特定できません。
そこで重要となるのが、プロによる「原因特定検査」です。散水試験では、特定の箇所に水をかけて実際に漏水が再現されるかを確認し、経路を絞り込んでいきます。赤外線カメラを使えば、壁内部の温度変化から水分の滞留を可視化でき、原因箇所の推定精度が格段に高まります。目に見えない部分にこそ、解決の糸口が隠れているのです。
プロが用いる診断技術(散水・赤外線・ドローン)
近年では、雨漏り診断に用いる技術も大きく進化しています。特にドローンの活用は、高所や傾斜屋根など点検が難しい場所の撮影に威力を発揮します。高精度のカメラでひび割れやシーリングの剥離などを確認でき、足場を組まずに安全・迅速な調査が可能です。
また、赤外線サーモグラフィによる診断は、建物表面の微妙な温度差を読み取り、内部の水分滞留や断熱材の濡れを特定します。さらに、図面と照らし合わせた浸水シミュレーションを行う業者もあり、再発リスクを根本から断ち切る手助けとなります。
こうした総合診断を取り入れることで、対処療法ではなく、原因除去の根本対応が実現します。
再発防止のために導入したい定期点検と報告書
一度雨漏りが起きた工場では、定期点検の導入が再発防止に直結します。とくに季節の変わり目や台風・豪雨の多い時期の前後に点検を行うことで、小さな異変を見逃さずに早期対処できます。
実際に、多くの工場が「年1〜2回」の点検で深刻なトラブルを回避しています。
また、点検のたびに「報告書」を作成してもらうことも重要です。写真付きの記録があれば、前回との違いや経年変化を把握しやすくなり、将来の補修計画や予算組みにも役立ちます。複数の点検記録を蓄積しておけば、仮に雨漏りが再発した場合でも、診断のスピードと精度が大幅に向上します。
「転ばぬ先の点検」こそが、雨漏りから工場を守る最善策です。
▼合わせて読みたい▼
雨漏り119とは?もしもの時に頼りになる雨漏りのスペシャリスト
雨漏り再発でお悩みならマルヤマへ!屋根以外の原因も徹底診断いたします

「屋根は直したのに雨漏りが止まらない…」そんなときは、外壁やシーリング、配管周辺といった“見えない盲点”が原因かもしれません。工場の雨漏りは複合的に発生するのが一般的で、屋根だけ補修しても根本解決にはならないことが多いのです。
プ株式会社マルヤマ/プロタイムズ豊田永覚店では、屋根はもちろん外壁・シーリング・配管取り合い部まで総合的に調査。赤外線カメラや散水試験、ドローン診断など最新技術を駆使し、原因を特定・可視化。見た目だけでは判断できないリスクを事前に防ぎます。
– 総合診断で“複数の雨漏り原因”を一括チェック
– 部分補修から長期的な再施工計画まで柔軟に対応
– 点検報告書による履歴管理で、将来の予算組みにも安心
お問い合わせは フォーム・メール・電話で受付中。ショールームへの来店予約もお気軽にどうぞ。雨漏りを「繰り返さない」対策は、マルヤマの総合診断から始まります。
人気記事

古い家の外壁は何が多い?外壁の種類と特徴を徹底解説
スタッフブログをご覧いただきありがとうございます! 愛...

グリシェイドグラッサ屋根材塗装ガイド:耐久性向上の秘訣と業者の選び方
スタッフブログをご覧いただきありがとうございます! 愛...

外壁の汚れが気になる!排気ガスや鉄粉の汚れは落とせる?対策方法は?
スタッフブログをご覧いただきありがとうございます! 愛...


 0120-578-576
0120-578-576